
個を解き放つ組織変革をマインドフルカフェ®︎ から
組織変革支援のとんがりチーム®︎ 研究所を主宰する AKI(野口正明)さんは、いまマインドフルカフェ®︎ という、個人やチームのオーガニックな変容を促すプログラムを世の中に広めようとしています。
日本のあらゆる組織で、個々の働き方やチーム運営のしかたなど新しい形を模索している方が多くいると思います。
組織の中で個の存在はどのように活かせるのか?AKIさんが今まで、どのような経験から、そこに行き着き、マインドフルカフェ®︎ で何を実現しようとしているか?とんがりチーム®︎研究所の「とんがり」とは何か?などを聞いてみました。
■はねっ返り上司が組織を変えた!
―どうして組織変革コンサルタントの道に進むようになったんですか?
AKI:大学を卒業して、大手食品メーカーに就職しました。最初、配属された部署は商品開発で、知識も経験もないから何もできなかったです。それから工場に異動になって生産管理みたいな仕事をして。過労死が出るくらい忙しい職場で、そこで組織変革を体験したのが、僕のいまにつながる原点なんです。
―どんな組織変革だったんですか?
AKI:シンプルなことなんだけど、その当時の業務を回すには、システムは古びてボロボロで、人員も圧倒的に足りなかった。そういう環境の中でも工場のオペレーションを続けていくには、人間が機械のようになりきって、定常の2倍くらいの時間を投入してカバーせざるを得ない状況だったんです。
つまり、人の犠牲の上によって成り立っていたので、当時はまだ過労死という言葉さえ無かったんだけど、どうも過去、二人ぐらい死んでいるらしい、でもそういうことさえ組織の中では伏せられてしまっていたんです。
―どんなことをしたんですか?
AKI:上司に、はねっ返り社員がいたんです。その人は本社にかけ合って、システムを改善したり、人を増やしたりを先導したのです。特別なことをしたわけではなく、当たり前のことをしたんだけど、それまで地獄の世界を見てきた身からするとスゴイ変革ですよね。もちろん、その上司と周囲の摩擦や軋轢はすごいものがありましたけど。でも、この上司との歩みが、いまの道に進むきっかけになりました。言ってはならないと思われていた問題もこうやって変えられるんだという感動体験ですね。
■トップがダメでも組織は変えられる!
―はねっ返り上司は工場のトップだったんですか?
AKI:いや、工場長は別にいて、その人は、朝来たら新聞をゆっくり読んで、日中は場内をちょっとふらふらしたり、雑談したりして、毎日17時になったらあがって、会社の交際費で飲みに行くみたいな生活(笑)。だから若手社員の過労死レベルの仕事量のことも全然わかってない。
そこで、はねっ返りの一課長が全部自分で動いて本社動かして、お金を投資させてって言うのを見て、たったひとりで始めたとしても、色んな人を巻き込んでいってネットワークをつくることで、かなりデカイことがやれるんだ!と思いました。
―その工場は組織変革によって業績は上がったんですか?
AKI:従来は、ひとり一人がギリギリの状態でやってたので、よくミスも起きて、例えば原料とか包装資材の調達ミスとかあるとラインが止まるんです。そうすると200人ぐらいの現場の人たちが製造できずに待っている、そういう事が頻発すると当然生産量も減るし経費もかさむ。それが変革によって普通になったんだけど、普通になっただけで、前と比べるとすごい業績アップということになりますよね(笑)。
―その工場長は首になったりとかですか?
AKI:いや全然、どんどん偉くなって(笑)。組織ってそう言うものかもしれません。社長賞とか取ったりしても、手柄は工場長に行っちゃうみたいな。
―理不尽ですよね?
工場に勤務しているときに、激務が祟り、からだを壊して1カ月入院したんです。
その時はこれで死んでも本望ぐらいに思っていたのですが、そのタイミングで子供が生まれて、入院中に今後の人生を考えるきっかけになりました。そのあと自分で希望をだして人事部に異動したんです。
―人事部に異動したいと思ったのは具体的に何ができると考えたんですか?
AKI:一人ひとりの力を掛け合わせてチームとして、一人では出来ないことを、どんどんやれたら、みんな楽しいし、そんなチームが会社中に溢れたら、業績もあがるだろうし、そんなことをやりたかったんです。実際はそんな仕事では全くなかったんだけど(笑)。

組織の未来をひらく創発ワークショップ-「ひらめき」を生むチーム30の秘訣
■「とんがり」さんをうまく使わないと組織に未来はない!
―「とんがり」とはどういう事を指しているのでしょうか?
AKI:組織の中では、一見、秩序を乱す出る杭のように見えるけど、実は変革や創造のタネになるようなもの。僕の1冊目の本は組織内における「とんがり」さん達をフィーチャーして、7人登場するんだけど、そのうちの一人はあの工場のはねっ返り上司なんだよね。
その人は活躍のわりには、あまり評価されてなかった。そういう人たちをうまく使わない限り組織に未来は無い。
昔のように、これをやればこれだけの業績が出ますみたいなことが描ける世界では「とんがり」さんは邪魔になったかもしれないけど、どんだけやったって成果が上がるかどうかわからない不透明な時代には、やっぱり従来と違うエネルギーを持ち込まないと突破できない。
実際、はねっ返り上司の実例を見て、こうゆう人が必要なんだなと言うのは30年前から考えていました。でも、「とんがり」さんはたいてい組織で疎外されているという現状を見るにつけ、こういうなきものにされている人たちをどれだけ表舞台に上げられるかっていうのが変革の大事な要素になると考えるようになりました。
いまの仕事でも、例えば対話をしようというときに最初からあきらかに違和感を漂わせ、すごい目つきで参加している人とかいるとまず注目するんです。何かきっとエネルギーがあるだろうって。実際はただの皮肉屋だったり、することも少なくないのだけど、そういう負のエネルギーを持っているような人を掘り出していくと、実はこうゆう想いが背景にあって、それが認められないためにくすぶってるみたいなことが見えたら、それをうまく引き出すみたいなことはよくやりますね。
―なるほどそういうのが「とんがり」なんですね
AKI:いまの話はある特定の人の場合を話しましたが、実はすべての人の一部に「とんがり」の要素はあるんじゃないかと思ってるんです。
―新たな「とんがり」さんを増殖したいということですか?
AKI:そう!一人ひとりの内部に眠ってる「とんがり」を掘り出して、それぞれの「とんがり」同士がかけ合わさったときに、自己組織化的な動きの中でより面白いチームが立ち現れてくるのが理想。
■自己組織化と日本人の特性は相性がいい

―自己組織化ってなんですか?
AKI:複雑系科学の用語なんだけど、組織は自律的に組織化し、出現するシステムだって捉える考え方です。つまり、組織の責任者がこういう方向に持っていこうと強制力を効かせなくても、メンバーがお互いフラットに関わりあいながら、変化していく感じ。だから、ある形で固定化されることなく常に変容し続けるのですね。
―シュタイナーだと組織にも有機体という言葉を使うんですが同じ意味ですね。
AKI:そうそう、これまでの組織観って機械論が主流で、だからピラミッド組織なり、あるいはマトリックス組織とかね。全部機械論なんですよ。目標を達成するのに、最も合理的な組織を機械みたいに設計して、こんな入力を行えば、これだけの出力ができますという前提に立っている。そうではなくて、自分たちの縦横無尽な関わりの中でよい出力に向けた試行錯誤をしていくんです。
―チームを変革するときに個々の判断力、決断力がないと進まないと思うのですが、その力が日本人は弱いように思うのですがどうしたらいいですか?
AKI:僕は最初に入った日本の食品メーカーからバリバリの米国企業に移籍したんですよ。そこで、特にトップ層の個々人が、合理的・戦略的な思考を武器に、主導する力をまざまざと見せつけられましたね。で、自分でも必死に学んで結構できるようになりました。
多くの人たちも成果主義などの環境下で個の力が鍛えられた部分はあると思います。もっともこの土俵ではやっぱり欧米人には概してかなわないですけど。でもね、われわれには黙っていても協力し合うような集合的文化が共有されてます。さっきの文脈で言えば、日本人がもう少し「とんがり」を出せるようになれば、「自己組織化」においては大いにアドバンテッジがあるはず!
■自己組織化への第一歩目
―マインドフルカフェ®︎ とはこの自己組織化につながるんでしょうか?
AKI:はい。自己組織化の第一歩目とも言えますね。組織の変革プロセスを描くときに一番苦労するのが一歩目を踏み出すところなんですよ。多くの人たちは、組織の中では自分の大事な部分を封印している。
だから、あなたらしさって何?あなたの在り方はどう?とかいきなり聞かれても答えられない、そもそもそんなこと考えることもしてないし、認識をしたとたんに組織との不一致が起きてしまうリスクがある。なので、合理的に自分を押し殺している。
その点、手前味噌ながらマインドフルカフェ®︎ のプログラムはいいんですよ(笑)。オープンかつ和やかなカフェっぽい雰囲気で、丁寧にそこに触るから。
自分らしい「在り方」を深く掘っていく行為って、個人にとっても、組織側にとっても、さっき言った理由で、リスク満載ですよね。その蓋を開けてしまったら、終わりなきジブン探しの旅に出るような。
そこまではせず、自分らしい「在り方」をまずザックリと把握し直して、実は目の前の仕事においても、この「在り方」を反映させることは十分にできるってことを、自分でリアルなストーリーとして創る。しかも、ひとりに閉じるのでなく、そこに集まった人たちと対話を通して創っていくみたいな体験があると、それが一歩目につながるだろうと考えています。
マインドフルカフェ®︎ をやってみて実感するのは、お手軽なんだけど、その一方でかなり本質的と言うか、なかなか両立しにくい二つの要素を統合してるところが大きな特長なんです。
■あらゆる層に有効なマインドフルカフェ®︎
―マインドフルカフェ®︎ をどんな人に受けてもらいたいですか?年齢層とか?
AKI:構想し始めたときは、若い層を考えていました。組織の抑圧構造の中で自分らしさを押し殺している人向けということだったんだけど、これってどの層にもあるな!と
多くの企業で、若手層の育成・活用と同じくらい、あるいはそれ以上に問題意識が持たれているのが、50代の定年前の人たちなんですよね。
50歳過ぎると、偉くなる人は役員とかに上り詰めるんだけど、ほとんどの人はそうではないので、役職も役職定年とかあって給料も下がります。そんな中、モチベーションがどんどん低下しているというのです。
―それは企業にとっても悩みのタネですね?
AKI:そうなんですよ。この層の人たちが幸せにならなければ、企業も社会もよくならない。若い人たちも自分たちの将来の姿とだぶらせてるところもあるだろうし。
50代の人たちにマインドフルカフェ®︎ をやるときは目の前の仕事だけでなく、もっと広い視点で、地域コミュニティとかボランティアやサークル活動といったものも広義の仕事と捉えて、自分らしい「在り方」をどう発揮するかのようなアプローチもオプションとして用意しています。
人生100年時代で、よりよく生き、働き続けるという観点からも、マインドフルカフェ®︎ は役立つと考えています。
―マインドフルカフェ®︎ は主要なメンバーが四人ですよね。なんで四人でやろうと考えたんですか?
AKI:企業ビジネスの世界一筋でやってきた僕と、スモールビジネスの事業家としてやってきた塚本サイコさんが、ともに「在り方」をベースにした働き方の再構築のようなことを考えていることが、未来を先取りするコミュニティである藤野でのプロジェクト発表会でわかったのが起点となりました。
まったく異なるバックグランドの人間が同じような問題意識を持ってやっていたということは、きっと普遍性があるんだろうと感じたんです。
さらに、マインドフルカフェ®︎ には、参加者の人数分だけの多様性があるということをベースに置いています。それをうまく伝えていくためにも異なるキャラ同士ででやった方がいいと考えたんです。
最初は二人だったんだけど、また同様の問題意識をもって「自分史」という領域でやっている柳澤史樹さんと出会い、彼もまた我々二人とは全然違う、社会活動も含めたところで活躍している。そして、彼の友人であり心理学者の竹田葉留美さんという今度はアカデミア世界の住人も加わって、一層多様性が広がる布陣になりました!
■マインドフルカフェ®︎ で自分の「とんがり」に気づく
―マインドフルカフェ®︎ は個人の「とんがり」を伸ばすようなプログラムですか?
AKI:プログラム自体は、伸ばすというよりは気づくという感じです。これまでの時代は、組織の中でとんがってしまうとそれは損でしかありませんでした。だから、自分の「とんがり」を隠したり、丸めるというのは本人にとって合理的な判断だったと思います。
でも、「とんがり」が求められる時代に少しずつ動いていることは間違いない。その「とんがり」に気づき、育くみ、自分自身と組織のために解き放っていくお手伝いをますますやっていきたいですね。
マインドフルカフェ®の詳細、導入に関するお問い合わせは

とんがりチーム®研究所 主宰 AKI(野口正明)
日・米の大手企業にて商品開発、生産管理、人事・人財開発の仕事を経て、組織風土改革支援のスコラ・コンサルトでプロセスデザイナーとして腕を磨く。約30年のビジネス経験を積み、2017年末にとんがりチーム®研究所を創業。1965年福岡市生まれ。早稲田大学政経学部政治学科卒業。NPOふじの里山くらぶ副理事長。
インタビュー、文 野崎正律
投稿者プロフィール

最新の投稿
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
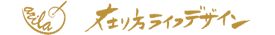
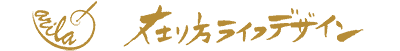














この記事へのコメントはありません。